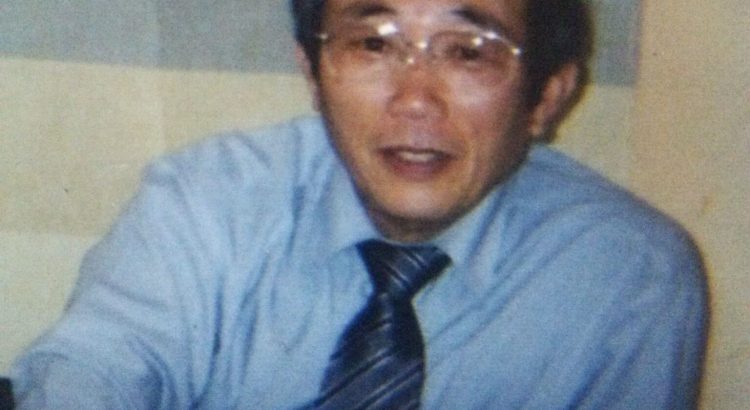暑い日が続き、秋が来ないのかと思われた、2016年10月2日、オースタット国際ホテル多治見にて、8回生学年同窓会が盛大に行われました。
同窓生112名と恩師、斎藤誠先生、安藤一郎先生、安藤富雄先生にご出席いただき、旧交を温め、豊かな時間を過ごしました。
不思議なもので、自分の年など忘れてしまい、高校生なってしまいます。正にタイムスリップです。 あの頃に戻り、色々な事をいっぱい、どんどん思い出します。
同窓生に会えるのは嬉しいものです。
生きていてこそ楽しい思いも出来るのですが、永眠した人が33名もいます。 冥福をお祈りいたします。
同窓生による講演会が2つありました。 「美しい老後について」川喜田節代さんから、今まさに私たちが直面している、認知症等のお話がありました。 もう手遅れかな? 心配したのは私だけかも。 もう一つは「ブラック企業について」吉田美喜夫さんからお話がありました。 とても深刻な社会問題だと思います。 お二人ともさすが講演のプロで、よく理解でき、勉強になりました。
今回の同窓会は、ちょっと変わっていて、途中、ミニジャズコンサートがありました。
とっても可愛いお嬢さん、粟田麻利子さん(34回生)に何曲か歌っていただき、おしゃれな気分にさせてもらいました。 校歌も一緒に歌うことが出来ました。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、次の4年後を約束し、クラス別の2次会に出発しました。
小嶋清子記(8回生)